カーボンニュートラル実現に向け、次世代エネルギーとして注目される水素。実用化に向けて自動車業界でも開発が進められているが、その課題や可能性はどのような部分にあるのか。
自動車ジャーナリスト・自動車経済評論家である著者が、企業動向や国の政策などを紐解きながら自動車業界の現状と未来に迫る連載「池田直渡の着眼大局」。第2回は、スーパー耐久シリーズ第2戦「NAPAC富士SUPER TEC24時間レース」で液体水素エンジン『カローラ』を完走させたトヨタの挑戦を振り返りながら、水素実用化に向けた取り組みの現在地を前後編に分けて解説する。
ルマン24時間にも水素カテゴリー
5月の第4週末、27~28日にかけて、スーパー耐久シリーズ第2戦「NAPAC富士SUPER TEC24時間レース」が富士スピードウェイで開催された。「なんで今頃になってそんな前のレースの話を」というなかれ、大変申し訳ないが、この記事のテーマは水素燃料の話であって、スーパー耐久シリーズ(S耐)のレースレポートではない。ということで「水素カローラ」の2年にわたるチャレンジの話がこれから始まる。
まずは、富士で意外な発表が行われた。世界3大レースのひとつ「ルマン24時間レース」の主催組織であるACO(フランス西部自動車クラブ)のピエール・フィヨン会長が100周年を記念して来日し、会見を開いた。
フィヨン会長は、2026年からルマン24時間レースに水素燃料車の参加を認めると発表した。世界耐久選手権(WEC)の花形レースであるルマンのトップカテゴリー「ルマン・ハイパーカー」(LMH)に参加が認められるのは燃料電池車(FCEV)と水素内燃機関(HICE)を搭載する車両。つまり2種類の水素自動車がエントリーすることになる。

世界の潮流を考えれば、やがてメジャーなレースに関しては、化石燃料での走行は減少していくことが予想される。WECでも、徐々にハイパーカーは水素とカーボンニュートラル燃料にシフトしていくであろうことが予見される。スポンサービジネスの側面が強いレースにおいて、環境に無関心となればスポンサー離れのリスクが大きい。
にしても「なんで、その発表を遠い極東の、しかも富士で?」と思うのは道理だ。空けて6月、ルマンに取材に行った同業者に聞くと、実はフランスでも「エスタイ」はすでに注目の的、要するにHICEとエスタイは、われわれが思うより、彼の国のモータースポーツファンに遥かに大きなインパクトを与えていたらしい。エスタイはHICEの本場と思われている。逆説的に言えば、フィヨン会長が日本に来たことこそがその証明でもある。
水素カローラ2年間の歩み
2年前の富士24時間で始動したトヨタのHICEチャレンジは、今年の富士で、ついに液体水素の採用に漕ぎつけたわけだが、ものには順番がある。まずは2年前から説明を始めよう。

過去2年間、トヨタがエントリーさせてきた水素カローラ「カローラH2コンセプト」は、『カローラスポーツ』のシャシーに、デンソーが開発した水素用インジェクターを装備した『GRヤリス』用のG16E-GTSユニットを搭載し、「燃タン」としては『MIRAI(ミライ)』の気体水素タンクを流用することで成立していた。
一方、スーパー耐久機構事務局(STO)は、こうしたメーカー製の実験車両をエントリーさせるために、新たに賞典外のST-Qという特殊な新クラスを新設する。通常のクラス分けと異なり、車両間のイコールコンディションを狙うのではなく、あくまでも実験車両を走らせるクラスである。
しかしこうした取り組みが、後に花開き、水素カローラの他にも、トヨタ、スバル、マツダ、日産、ホンダなどのカーボンニュートラル燃料(CNF)を使うワークス車両が続々とエントリーしていくことになり、今や一大勢力に育ちつつある。
肝心のカローラH2コンセプトは、初戦の富士では、最も下のクラス、ST-5の車両に小突き回されるところからスタートしたが、1戦毎にメキメキとポテンシャルを上げ、チャレンジ3年目となる今年の第一ラウンド「鈴鹿」の予選タイムでは、ついにひとつ上のST-4の全車両を上回り、ST-2やST-3の後ろの方を食うほどの速さを見せるに至った。とは言え、耐久レースである。予選はともかく、本番ではピットワークも含めた総合力が求められることになる。
気体水素のタンク内圧はなんと700気圧という超高圧。その圧力で水素を充填するには、大型トラック2台を要する大仕掛けになってしまう。ピットにそんなものは置けるはずもないので、特別に許可を取って、パドックの端に特設充填ポイントを設けてもらって運用した。
となれば、他チームが、ピットで給油している中で、カローラはピットレーンからわざわざ外のパドックまで出て、その隅っこまで安全速度で自走して初めて水素の充填が始まる。しかも限られたタンクにパンパンに高圧充填するので、ガソリンの様に短時間では充填できない。充填そのものにも当初は5分もかかっていた上に、一充填での航続距離が短いから、ストップ回数が他車より多い。回数が多く、充填時間が長く、充填場所が遠くて、しかもその間の走行に速度規制がある。ということで、コース上を走る速さはレース毎に進歩しているにも関わらず、一向に順位に結びつかず、賞典外とは言うものの、総合順位ではずっと煮え湯を飲まされてきた。

その解決のための画期的な手段こそが、今回の富士から投入された液体水素への転換である。まずは通常通りピットでの燃料補給を可能にすべきだ。すでに昨年の富士では液体水素タンクシステムのプロトタイプが展示されていたので、毎レースを戦いながらも次世代技術の開発は進んでいたとも言える。今回の富士から投入された液体水素の補給設備は、十分ピットに収まるので、他のレース車両同様ピットストップで補給できるようになった。
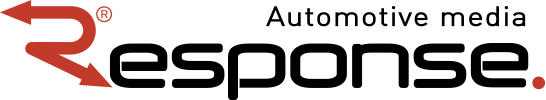













































![[15秒でわかる]メルセデスAMG『ピュアスピード』コンセプト…初のミトスブランド](/imgs/sq_l1/2012075.jpg)

