電動車の開発ではなにかとバッテリー(二次電池)の資源問題がついてまわる。3月に開催された「国際二次電池展」において、豊田通商、エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)によるセミナーが開かれた。講演内容をベースにあらためて二次電池関連資源開発の状況を整理する。
豊田通商のリチウム開発
豊田通商 金属本部COO(執行幹部) 片山昌治氏によれば、2023年、同社はアルゼンチン、フフイ州 オラロス塩湖による炭酸リチウム事業の生産能力を拡大する。
このプロジェクトそのものは2008年にスタートさせたものだ。電動車に必要な資源研究は産総研、トヨタとともに2006年には行っていた。オラロス塩湖での炭酸リチウム生産は、2015年から商業生産開始済み。2023年は、現在進めている拡張工事が完了し、生産能力が現在の1万7500トンから4万2500トンに引き上げられるタイミングである。
このプロジェクトの特徴は、アルゼンチンで精製・生産された炭酸リチウムを日本に輸入して、電池グレードの水酸化リチウムを製造することも含まれている。水酸化リチウムの製造工場は福島県双葉町に建設されている。
水酸化リチウムは、正極材にコバルトを減らしてニッケルを多く使うハイニッケル(NMC811)系のバッテリーの原料として必要なものだ。豊田通商では、ハイニッケルの需要を見据えて水酸化リチウムの工場にも投資している。
原料となる炭酸リチウムは、鉱石を採掘して粉砕・精製する方法と、かん水をくみ上げ蒸発・精製する方法がある。前者の資源はオーストラリアや中国に集中しており、全体の半分がオーストラリアにあるとされている。後者は南米が主な産出地で、塩湖からとれるリチウムがこれに属する。鉱石から作られるリチウムは採掘や粉砕工程、精製の前の焙焼など工程が多くコストが割高になる傾向だ。塩湖由来の炭酸リチウムが1トンあたり4500ドル程度のところ、鉱石由来では5539ドルだという。
採掘・精製にかかるCO2排出量は、鉱石由来が9.3トン、塩湖由来が2.8トンと大きな開きがある。ただし、炭酸リチウムの製造にかかる日数は、鉱石由来が1か月前後という工程で済むのに対して、塩湖由来は貯留池で蒸発させる工程が300日ほど必要になる。
それぞれ一長一短ある。蒸発工程は、薄膜や電解などの方法も研究されているが研究段階でコスト的にも実用は見えていない。片山氏によれば、今後、カーボンプライシングなどで塩湖由来のニーズが高まる可能性もあるが、現状それで売買や契約が決まることはないという。
リチウムの資源状況
リチウムの埋蔵量は約1億1700万トンといわれている。その42%がチリ、26%がオーストラリア、アルゼンチンが10%と続く。中国は7%と4位だ。採掘量は2022年で約70万トン。およそ半分がオーストラリアで2位のチリが約3割。中国10%、アルゼンチンが8%と続く。埋蔵量、採掘量ともにオーストラリアとチリが群を抜いているが、炭酸リチウムなど工業グレードリチウムの生産量では中国がそのほとんどを占める。
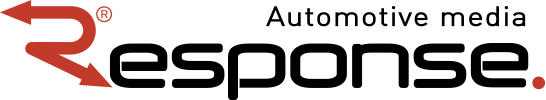










![[15秒でわかる]KGモーターズ『mibot』…超小型モビリティを開発中](/imgs/sq_m_l1/2012071.jpg)

![アフリカの自動車産業、地域ごとの市場特性とビジネス展開のポイント…豊田通商 渡邊剛氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/1990009.jpg)









