将棋AIの父、「PONANZA」の開発者山本一成氏が、AIおよび制御システムの研究者である青木俊介氏とともに起業した「TURING」(チューリング)が製造した、レベル2自動運転車の1号車(1st TURING CAR)の売約が決まった。
1号車完成のリリースが1月20日。さっそく取材すべく連絡をとり日程調整をしていたところ、取材日直前に「さっそく売れた」との一報を入手。売買価格は2000万円。1号車完成からわずか2週間ほどのスピード成約を果たした。TURINGの創業は2021年だが、翌22年7月に10億円の資金調達を発表し、「テスラを超えるメーカーを目指す」とぶち上げた。そこから、プロトタイプの開発が始まり、10月には北海道一周の無人走行実験を成功させている。
筆者が最初に同社を訪れたのは昨年春。オフィスは新川崎にあり車両も中古のエスティマに秋葉原で売っているWebカメラとノートPCで制御される極めてシンプルなものだった。それがわずか1年でワンオフの限定販売とはいえ、製品まで仕上げ買い手までついた。この機動力と実績は大きい。専門家視線ではベンチャーのご祝儀相場、功を焦って失速するのでは、といった意見もあろうかと思うが、実際に成し遂げたものの前ではどんな意見も説得力を欠く。
■開発ベンチマークはテスラのAP
「1st TURING CAR」は、レクサス『RX450h』(ハイブリッド)をベースに、TURINGが開発した自動運転システムをビルトインしたもの。自動運転レベルはL2相当だ。自動運行装置ではないため、システムは車両への後付け装置の扱いとなる。車検などの記載変更なくメーカーの型式で登録される(ドラレコを後付けする扱いと同じと考えてもよい)。今回販売する車両のオーナーはTURINGとの契約となり、車検整備その他のアフターサポート、メンテナンスはTURINGがすべての窓口となり、ディーラーやメーカーと同等な支援を提供される。
ベース車両には「Lexus Safety System +」というADAS機能が備わっている。1st TURING CARのAI自動運転機能は、メーカーのADAS機能(前車追従、速度制御、停止制御、レーンキープ、ハンドル制御など)をオーバーライドしている。ただし、保安基準と型式を守るための安全機能は残る。
レベル2なのでAIの制御で動いている状態でもドライバーの監視下にあることが前提だ。制御のメインはフロントの2台のカメラ。これに車両が持つセンサー群の情報もみながら、L2の運転支援を行う。カメラは2つあるがステレオカメラではなく、魚眼と普通のレンズのカメラを搭載する。魚眼レンズはフロント周辺環境、たとえば車線変更してくる車の検知などを広域センシングする。現状、AIが制御のために識別しているのはセンターライン、縁石、前方の車(2台)だ。
取材では「1st TURING CAR」のプロトタイプ(売約済みの車体ではない)に試乗することができた。開発者はテスラのAP(オートパイロット:L2)をベンチマークとしているといい、コーナリングのトレースはなめらかと言っていいだろう。手元の白線だけをみながら小刻みに介入が入るというより、最初にラインを見据えて切り込むような制御が入る。
加減速(アクセル・ブレーキ)の制御、左右の制御(ハンドル)は、現在市販されている追従型クルーズコントロールやレベル2運転支援との違いは感じられない。ただ、自動運転の起動や速度設定、画面UIなどは粗削りなところがある。慣れや好みで評価が変わりそうだ。
 カメラは2つ使うがステレオカメラではなく魚眼と普通レンズの2種
カメラは2つ使うがステレオカメラではなく魚眼と普通レンズの2種■2025年には自社開発プラットフォームのEVを100台つくる
TURINGは「1st TURING CAR」を1台のみの限定車両として捉えている。製品として販売はしたが、この形での販売は継続しない予定だ。次に目指すのは独自プラットフォームによるオリジナルの自動運転EVだという。冒頭に述べた2025年までに販売を開始する車両。目標販売台数は100台としている。車両のスペックやデザインは未定だが、彼らの戦略スパンではこれらは走りながら決めていけばよいもので、決まっていくものでもある。
ただし、目標達成のマイルストーンはできているそうだ。まず2023年度内に、独自のEVプラットフォームを完成させる。そのための工場、生産設備の準備は始まっている。バッテリー、モーター、インバーターやバッテリー温度管理、充電管理、統合ECUなどは自社設計・自社製造にこだわる。上物であるボディエクステリア、内装、IVIなどはパートナーによる調達や製造を考えている。パートナーは海外企業、サプライヤーも視野に入れており、必要ならば工場ごとの委託や買収も選択肢だという。
テスラもGMのフリーモント工場の買収から本格的なメーカーとして旗揚げした。同社も類似のスキームで成長する可能性はあるだろう。だが、それだけではテスラの後追いでしかない。あるいは中国で乱立した自動車メーカーやファブレスメーカーと同じともいえる。とくに後者の場合、グローバル市場でみたらレッドオーシャンであり淘汰さえ始まっている。
 TURINGは2025年までに独自開発のEVを100台作る
TURINGは2025年までに独自開発のEVを100台作る
■AI・自動運転を強味にするセグメント戦略
取材に応じてくれた田中大介氏(取締役 COO)によれば、「TURINGの価値の源泉はAIにある」という。「製造業や自動車についてはまだ赤ん坊のような存在で学ぶことだらけだがAI技術についてはOEMに持っていないものを持っている自負がある」(田中氏)。この戦略は投資にも現れている。
独自プラットフォームを製造するための工場用地はすでに確保しているが、自動運転AI開発への投資も怠っていない。プロタイプやECU(なお、彼らの車載AI ECUはアプトポッドのエッジユニットを使っていた)開発のほか、走行データの収集も積極的に行なっている。AI活用においてデータ収集に適切な投資を行っているベンチャーはあまり多くない。時間とコストがかかるので新興企業ほど、AIモデルやアルゴリズム開発に注力しがちだ。限られた予算ではそうせざるを得ない必然もある。だが、近年のAI開発では学習データこそ、市場での成否を左右する重要な存在となっている。
じつは、同社のAIの学習において、テストコースで取れるものはすでにあまり多くないレベルに達している。HILSのようなシミュレーション開発環境も想定しながら、実車の走行データ、実環境のデータをいかに集めるかという戦略にフォーカスしている。大手メーカーは、コネクテッドサービスを契約した車両から(個人・個車を特定しない形で)データを収集し、学習データ等に役立てている。フィールドにプローブカーを持たないTURINGはこの手法は使えない。
TURINGではN-BOXを10台ほど、グーグルのストリートビューカーよろしく各地を毎日走らせている。彼らの自動運転はカメラ優先の「ビジョンポリシー」だ。高価な3D高精細マップや高価なLiDARに依存せずとも(自動運転が、3Dマップに依存する段階でLiDARなどスキャナーは必須のセンサーとなる)L5(完全自動運転)が目指せる。むしろ、高精細3Dマップに依存しているかぎり(マップやGPSが制約条件になるので)L5には到達不可能だともいえる。
完全自動運転に必要なのは「高性能なマルチセンシングシステムよりも、高性能な頭脳(AI)だ」と田中氏はいう。人間はほとんど視覚情報(音や重力などもあるが)で運転しているが、それでも現在の自動運転やADASよりも賢いと感じるだろう。認知や判断をする頭脳が優秀であれば視覚情報だけでAIによる自動運転はさらに進化可能という考え方だ。
■既存OEMが作らない車にチャンスがある
機械学習において、優秀な頭脳(AI)を活かすのは高度にフィルタリングされた(アノテーション、セグメンテーション、スクリーニング)大量のデータだ。不幸にもこのデータは巨大プラットフォーム、自動車ならば大手OEMに集中する。GAFAなどはこの重要性に古くから気づいているが、プラットフォーマーではないTURINGは、独自のアプローチでAI強化に取り組んでいる。
TURINGでは、2025年発売予定の車両は、最低でもテスラのオートパイロット(AP)レベルの機能は実装できると見ている。その中で、いま彼らがこだわっているのは信号機の認識だ。変則交差点、五叉路、複雑な矢印信号にも対応するモデルを自動運転AIに組み込もうとしている。信号機の認識はITSスポットなどインフラ協調型のソリューションがあるが、スポット以外の任意の信号、海外の信号機にも対応させるにはAI(機械学習系の手法)のほうが実用性が高くなる。
また田中氏は、「理想だが」と前置きしつつも「2030年には完全自動運転は実用化されていると思う。自分達もハンドルのない車が作りたいと思っているが、OEMにはハンドルのない車や完全自動運転車を作るモチベーションはないと思う。しかし、逆にそれがチャンスでもある」と考えている。
自動運転に対するTURINGの戦略は、既存OEMに違和感を感じるかもしれない。製造業が培ってきた安全思想に反するという意見もあるだろう。だが、これは自動運転に対するアプローチの違いであり技術や手法の是非の議論は馴染まない。
だからといって、TURINGはAI原理主義的な立場をとっているわけではない。「理想はハンドルがない車だが、現実には法規制の他社会的な受容をクリアしない技術はないと思っている。必要ならばLiDARも使うつもりでいる。実際、性能もよくなって安くもなっている。パートナー企業との学びやコミュニケーションを通じて落としどころはあると持っている」と田中氏はいう。
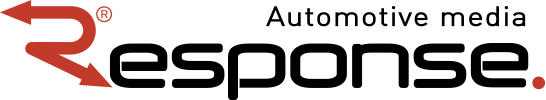




















![[15秒でわかる]KGモーターズ『mibot』…超小型モビリティを開発中](/imgs/sq_m_l1/2012071.jpg)


