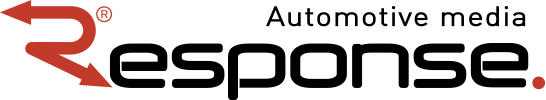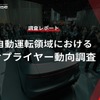mirai.Rsponseでは「自動運転ニーズ調査」と題し、調査レポートを作成した。
レポートは二部構成となっており、第一部では消費者の自動運転に対する理解度・受容性を理解するためのアンケート調査を行った。
第二部では各OEMの自動運転開発におけるロードマップとアライアンス状況を理解するためのデスクトップ調査を行った。
本記事では第二部で調査した、自動運転に関連する各OEMのアライアンス状況について紹介する。
調査目的・背景
COVID-19によるパンデミックを受け、私達の生活は一変した。人との接触を避けるために外出が制限され、インターネット上での買い物はより身近なものになった。外出制限の解除後も感染拡大防止のために、人との接触を極力避けた交通手段が意識されるようになった。すなわち物流の更なる自動化や、自動運転技術を活用したロボタクシーなどの、非接触型の移動手段に対するニーズがより一層強まった。こうした背景もあり、この世界的な自粛期間中にも自動運転領域で様々な新たな発展が見られた。
今回はそうした各社の取り組み状況を把握しやすくするために、2021年時点における各社のアライアンス状況を「自動運転カオスマップ」として可視化した。
調査対象
今回調査対象としたのは、基本的には各リージョン/分類において販売台数の多い、もしくは自動運転に関する取り組みにおいて具体的明言を行っている以下のOEMである。なお今回はCVCによる投資など、資本投入を行なっているだけでは提携・協業しているとは見なさないものとした。
日系
・トヨタ
・ホンダ
・日産
ドイツ系
・フォルクスワーゲングループ
・ダイムラー
・BMW
米国系
・GM
・フォード
・ステランティス
(※ステランティスは欧州系のPSAと欧州系/米国系であるFCAの対等合併によって誕生しており、どちらかと言うと欧州系の色が強いが、旧Big3のクライスラーを含むため、便宜上米国系に分類した)
中国系
・SAIC(上海汽車)
・BAIC(北京汽車)
・Geely(吉利汽車)
スタートアップ系
・テスラ
・NIO(上海蔚来汽車)
調査手法
調査は公開情報(各社の発表およびニュースなど)を元にファクトを収集し、それを整理・考察する形でレポートをまとめている。
カオスマップの作成方法として、上に挙げた各社と提携もしくは協業等をしているプレイヤーを所属カテゴリーごとに分類し、資本投資を伴う業務提携や、年を追うごとに提携・協業関係を強化しているなどの関係性があるプレイヤーについては、背景色を塗りつぶすことでその結びつきの強さが分かるようにした。
ロゴの大きさはそのプレイヤーの"存在感"を表現しており、今回調査対象とした複数OEMとの提携の数によって大きく表示している。
なお、CVCによる出資のみなど、出資しているだけでは「一緒に取り組んでいる」と見なさないという判断を行った。
全体サマリ
インテル(モービルアイ)とバイドゥ(百度、Baidu)がそれぞれ6社のOEMと何かしらの提携・協業を行っており、今回調査した中では最も多い提携・協業の数となった。
インテルについては傘下のモービルアイとOEMにおける提携・協業が全てで、モービルアイのマッピング技術やSoC、プロセッサー、自動運転ソフトウェアなどの提供を行っている。
Baiduについても車載ソフトウェアなどといった自動運転の“頭脳”となる部分に強みがあることと、同社が「Project Apollo(アポロ計画、阿波罗计划)」を打ち出していることが、多くのOEMとの提携・協業実現に大きく寄与していると考えられる。
その他、Bosch(ボッシュ)は4社のOEMと提携・協業しており、Nvidia(エヌビディア)、HERE(ヒア)、Tencent(テンセント)はそれぞれ3社のOEMと提携・協業をしていた。
なお、自動運転のトップランナーであるテスラを見てもわかるように、提携・協業の多さが必ずしも自動運転の先進度と比例するわけではないことも添えておきたい。
これは自動運転開発を突き詰めていくと、ソフトウェアの開発だけでは限界があり、どうしてもハードウェアの開発も必要になってくる部分があるからだろうと考えられる。
こうした内製化の動きは、GAFAと呼ばれる世界を代表するテックカンパニーにおいて顕著に見られる。例えばApple(アップル)であれば2007年に自社開発プロセッサをiPhoneに搭載し、2020年にはMacに自社開発のCPU「M1」を搭載し飛躍的な性能向上を実現させている。
Google(グーグル)においても自社開発したAIチップ「TPU」を活用し、Amazon(アマゾン)もAWSのサーバーに特化した自社開発ARMプロセッサ「AWS Gravition 2」を使用したクラウドサービスを提供することで一定の成功を収めており、Facebook(フェイスブック)も自然言語処理(NLP)に特化したAIチップを自社開発すると発表している。
自動車業界で自動運転開発のトップ集団に属するテスラもこうした流れに遅れず、2016年から自動運転用AIチップの開発を開始しており、電気自動車(EV)向けのリチウムイオンバッテリー(LiB)の開発においても内製化していくと発表している。
エグゼクティブサマリ
いずれにせよ、提携・協業の多さは自動運転に対するOEMの積極性の表れであることは間違いないと言えるだろう。しかし提携・協業の多さが自動運転開発の先行度合いと100%比例するわけではなく、自動運転開発を突き詰めていく中では内製化のニーズも一定あるだろうと予想され、GAFAやテスラの先行事例に見られるように、今後自動車業界においても自動運転を司る”頭脳”の領域を中心に、内製化の動きが拡がっていくことも十分に考えられる。
調査レポートのダウンロードおよび購入
プレミアム会員は以下から、調査レポートのダウンロードが可能です。
無料会員・シルバー会員につきましては以下より購入が可能です。