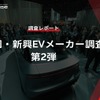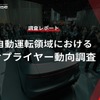mirai.Rsponseでは「自動運転ニーズ調査」と題し、調査レポートを作成した。
レポートは二部構成となっており、第一部では消費者の自動運転に対する理解度・受容性を理解するためのアンケート調査を行った。
第二部では各OEMの自動運転開発におけるロードマップとアライアンス状況を理解するためのデスクトップ調査を行った。
本記事では第二部で調査した、自動運転に関連する各OEMの自動運転ロードマップについて紹介する。
調査対象
今回調査対象としたのは、基本的には各リージョン/分類において販売台数の多い、もしくは自動運転に関する取り組みにおいて具体的明言を行っている以下のOEMである。
日系
・トヨタ
・ホンダ
・日産
ドイツ系
・フォルクスワーゲングループ
・ダイムラー
・BMW
米国系
・GM
・フォード
・ステランティス
(※ステランティスは欧州系のPSAと欧州系/米国系であるFCAの対等合併によって誕生しており、どちらかと言うと欧州系の色が強いが、旧Big3のクライスラーを含むため、便宜上米国系に分類した)
中国系
・SAIC(上海汽車)
・BAIC(北京汽車)
・Geely(吉利汽車)
スタートアップ系
・テスラ
・NIO(上海蔚来汽車)
調査手法
調査は公開情報(各社の発表およびニュースなど)を元にファクトを収集し、それを整理・考察する形でレポートをまとめている。
実用化ロードマップの作成方法として、縦軸に各OEM・横軸に西暦をとり、各社の自動運転実用化の状況を棒グラフで表現し、時系列で比較できるよう可視化した。
棒グラフの色は自動運転のレベル(基本的にSAE基準)で色分けし、同じ自動運転レベルであっても色が薄いものは「その自動運転レベルの実用化に向けて、具体的な取り組みを行なっていることが公開情報から明らかなもの」を示している。
色が濃いものは「その自動運転レベルの実用化がされたことが、公開情報から明らかなもの」を示している。
両社のいずれでもないその他の事項は濃色でも淡色でもない中間色で表現し、自動運転レベルを括弧で記載しているものは推測であることを示している(例:(Lv.3)の表記であれば、「自動運転レベル3だと推測される」と言う意味合い)。
なお、複数年にまたがる形で濃い色の棒グラフが存在する箇所があるが、これは例えばBMWのように「2025年から2030年の間に自動運転Lv.5を実用化する」と公表しているようなケースを表現している。
自動運転のレベルについて
自動運転Lv.1
フットオフが可能な自動運転。ドライバーは常にアクセル・ブレーキの操作を行う必要がなくなる。単一の部分的運転自動化で、代表的な実例としてはクルーズコントロールが挙げられる。
自動運転Lv.2
ハンズオフが可能な自動運転。ドライバーは常にステアリングを握る必要がない。複数の部分的運転自動化を指し、アダプティブクルーズコントロールやレーンキープコントロールなどがこれに該当する。日産の「プロパイロット」や、スバルの「アイサイト」などが実例として挙げられる。
自動運転Lv.3
アイズオフが可能な自動運転。ドライバーは常に前方を注視する必要がない。限られた条件下における自動運転のため「条件付き自動運転」とも呼ばれる。高速道路における車線変更なども含めた自動運転などがこれに該当し、ホンダの『レジェンド』やアウディの『A8』などが搭載する自動運転機能が実例として挙げられる。
自動運転Lv.4
マインドオフが可能な自動運転。ドライバーは常に運転のことを考える必要がなく、「高度自動運転」とも呼ばれる。基本的には自動運転システムが運転を行い、「自動運転制御不可能」とシステムが判断した場合にのみ、運転をドライバーに引き渡す。実例としてはAlphabet(アルファベット)傘下のWaymo(ウェイモ)が米国アリゾナ州で行う、クライスラー『パシフィカ』やジャガー『I-PACE』をベース車両としたロボタクシーや、中国のスタートアップであるPony.ai(ポニーAI)が米国や中国で行う、現代自動車の『Kona(コナ)』をベース車両としたロボタクシーなどが挙げられる。
自動運転Lv.5
完全自動運転。ドライバーによる運転への関与が全く不要なことから、車両にはステアリング自体の存在が不要になる。Waymo(ウェイモ)が試験走行させている『Google Car(グーグルカー)』が実例として挙げられる。
調査サマリ
今回調査した中で最も自動運転の実用化が進んでいたのはテスラであった。テスラは当初「2020年に完全自動運転(自動運転Lv.5)を実用化する」と明言しており、その目標からは遅れているものの、依然として全OEMの中で最も早い「2021年~2024年までに完全自動運転を実現する」と明言している。
テスラに次いで自動運転Lv.5の実現を早期に明言しているのがBMWで、2025年から2030年までの5年間の間で完全自動運転を実用化すると発表している。
その次に先行しているのがVW(フォルクスワーゲングループ)とGM(ゼネラルモーターズ)で、2021年には自動運転Lv.4を実現させると公表している。
日系OEMの中ではホンダが先行しており、2020年に『レジェンド』で世界初の自動運転Lv.3の片式認証取得を実現し、2021年から2025年までの間に自動運転Lv.4を実現するとしている。同社の杉本エグゼクティブチーフエンジニアは、ホンダを「カメ」に、競合他社を「ウサギ」にたとえ、「ホンダには安全については真摯・愚直に取り組む文化があり、結果的にウサギを追い越すことができたと思う」と、自動運転技術の実用化が着実に進んでいることをアピールしている。
今回調査した限りではトヨタの自動運転Lv.4以上の実現に関する明言は見受けられなかったが、ウーブンシティが2025年までに竣工・入居開始がされることから、実質2025年までに局地的に自動運転Lv.4もしくはLv.5が実現されるものと推測される
中国勢も比較的先行しており、SAIC(上海汽車)とBAIC(北京汽車)の両者は、2024年には自動運転Lv.4を実用化すると明言している。これには中国政府の方針も強く影響していると思われ、中国政府は以下に挙げる自動運転の技術ロードマップを打ち出している。
・2020年までに自動運転Lv.1/2相当を新車販売の50%に搭載(ADAS、高速道路での一部自動運転、自動駐車等)
・2025年までに自動運転Lv.3相当を新車販売の20%に搭載(走行可能エリアを交差点・国道等に拡大)
・2030年までに自動運転Lv.4/5相当を新車販売の10%に搭載(走行可能エリアを市街地全体に拡大)
エグエクティブサマリ
現在はテスラが自動運転の実用化で先行しており、自動車OEMの中では最も早く完全自動運転(自動運転Lv.5)を実現すると思われる。次いでBMWとVWグループ(Audi)、GMが先行していると見ることができ、日系OEMと中国勢も拮抗してその後に続いている。
自動運転は車両やソフトウェアの開発だけではなく、法的なハードルもあるため、それを実現するための環境整備を進めていく必要があります。これらを三位一体で進められたOEMもしくはプレイヤーが、完全自動運転を最も早く実用化させると言えるだろう。
調査レポートのダウンロードおよび購入
プレミアム会員は以下から、調査レポートのダウンロードが可能です。
無料会員・シルバー会員につきましては以下より購入が可能です。